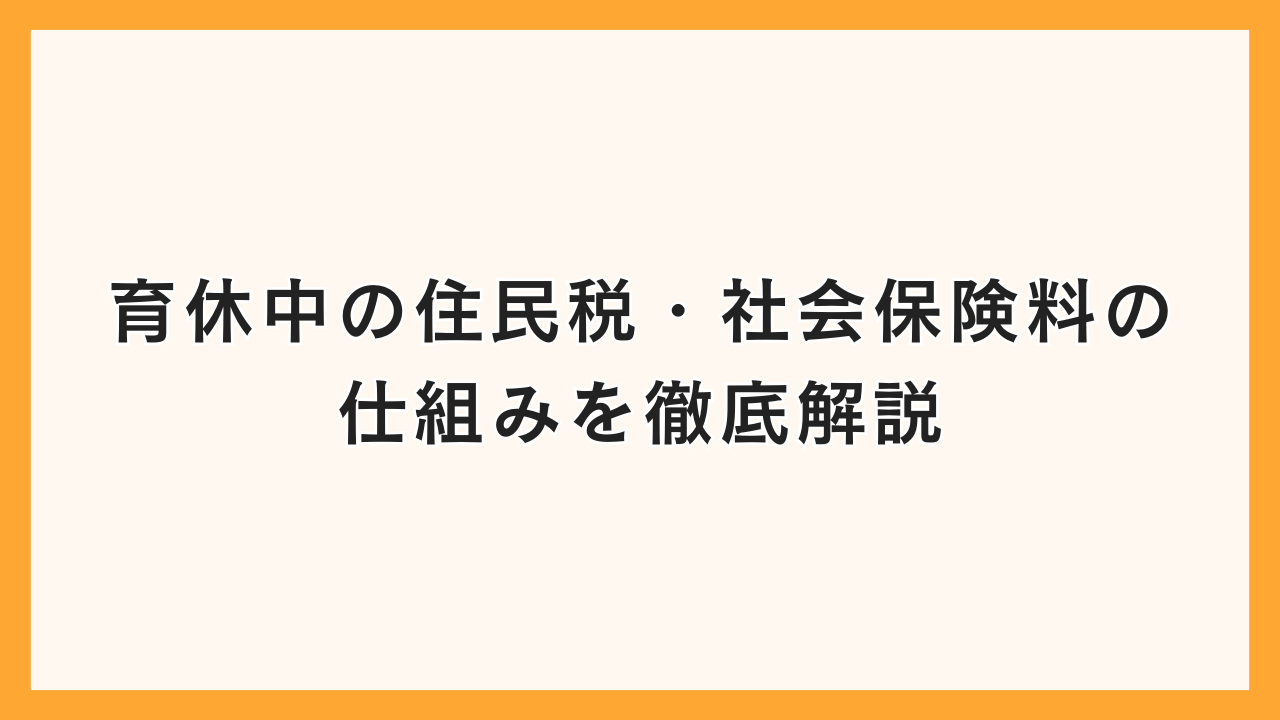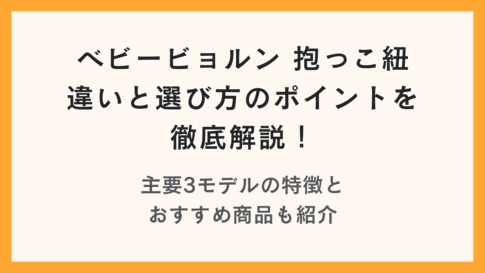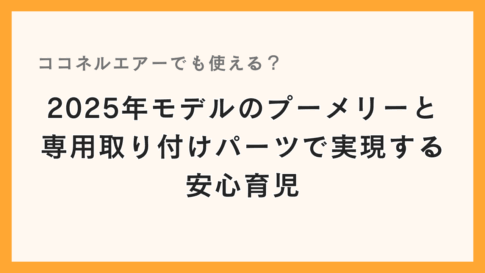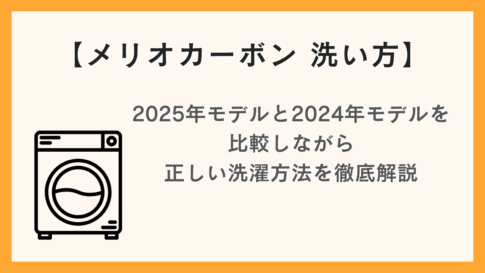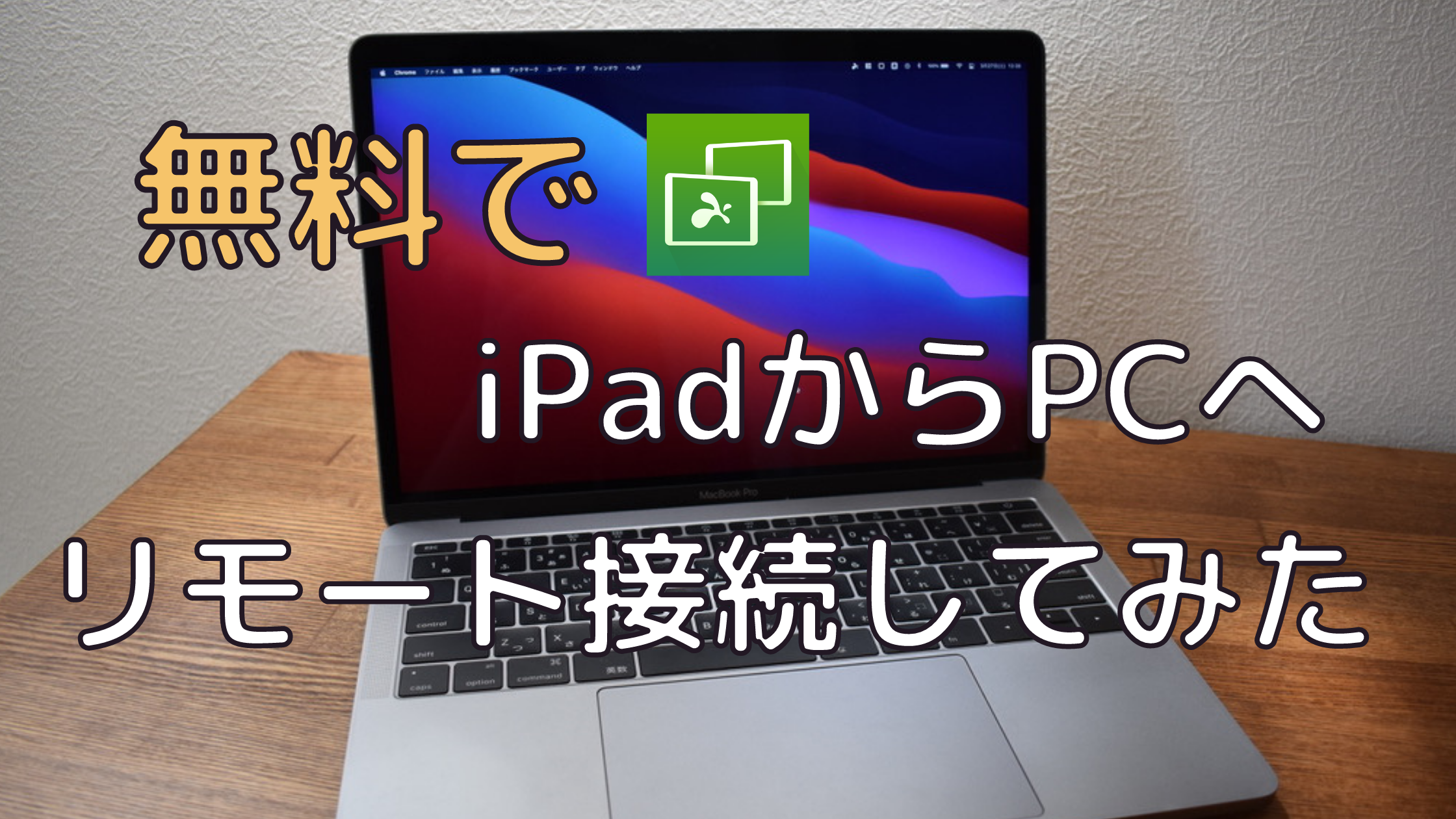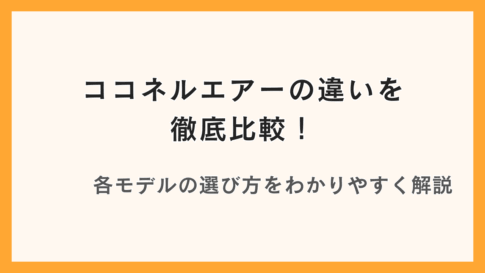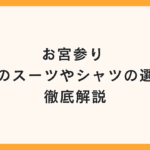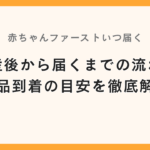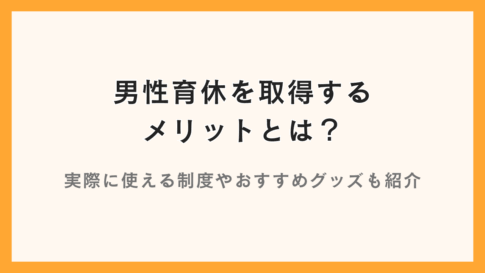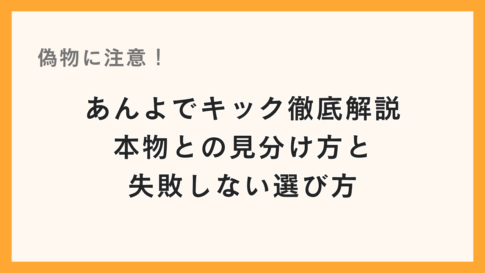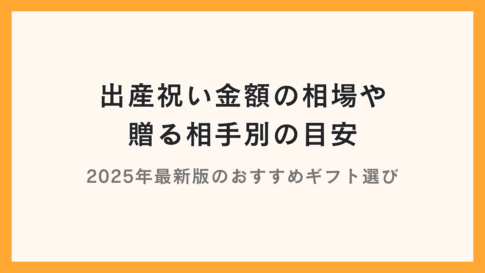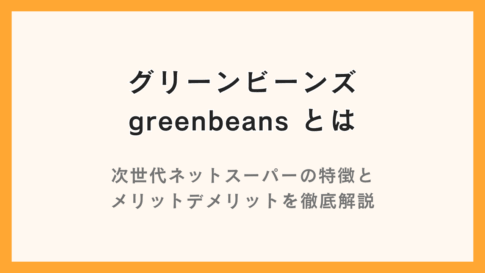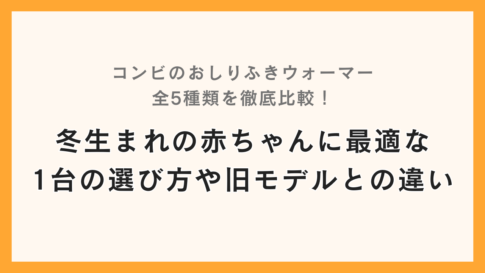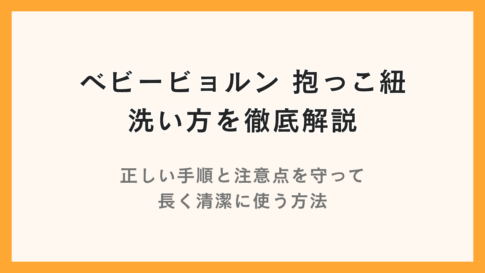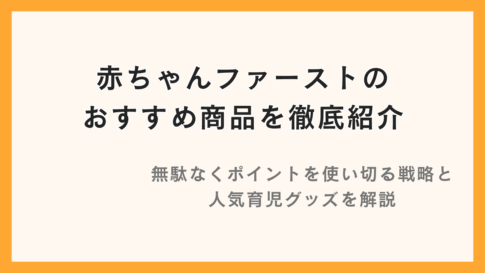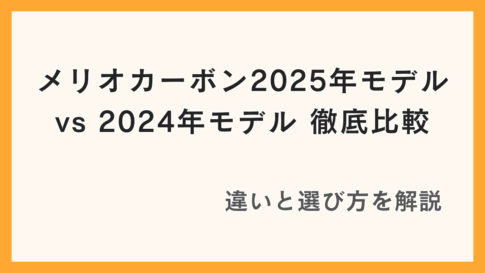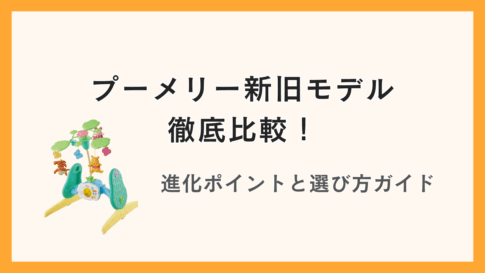目次
育休中の住民税はどうなるのか
育休に入ると給与がなくなるため、税金の支払いがどうなるのか不安に感じる方は多いです。住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、育休中であっても支払い義務は残ります。育児休業給付金は非課税なので、課税対象にはなりません。
支払いが残るのは結構ショックですよね…
住民税の納付方法
育休開始時期によって住民税の納付方法が変わります。- 1月~5月に育休を開始した場合は、育休前最後の給与から5月分までの住民税がまとめて天引きされます。6月以降は自治体から送られる納付書により、分割で支払うことになります。
- 6月~12月に育休を開始した場合は、給与天引きができず普通徴収に切り替わります。金融機関やコンビニ、口座振替、クレジットカードなどでの支払いが可能です。
育休中の社会保険料は免除される
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、育休中に勤務先を通じて申請を行えば免除されます。免除期間中も将来の年金額には影響せず、支払ったものと同じ扱いになります。これにより、経済的な負担が大きく軽減される仕組みです。
社会保険料免除は助かります…
納付スケジュールを把握することが大切
住民税は一括請求や分割納付になる場合があり、まとまった金額が必要になるケースがあります。育休前に余裕をもって貯蓄を準備しておくと安心です。ここで役立つのが家計管理グッズです。
紙の家計簿は支出の把握に役立ち、住民税や育児にかかる費用を見直すのに最適です。
育休中におすすめの便利アイテム
育休中は赤ちゃんとの時間が増える一方で、節約や効率的な生活も大切です。手続きは会社と自治体に確認を
住民税の納付や社会保険料の免除は、勤務先や自治体の手続きが関わります。特に社会保険料免除は会社から年金事務所への申請が必要となるため、事前に人事部へ確認しておくことが重要です。まとめ
育休中でも住民税の納付は必要ですが、社会保険料は免除される仕組みがあります。- 住民税は前年の所得に基づいて課税されるため支払いが必要
- 納付方法は育休開始月によって異なる
- 社会保険料は会社の申請で免除される
- 家計管理や育児アイテムを活用すると負担を軽減できる
これらを正しく理解し、家計に無理のないよう計画を立てて育休を過ごすことが大切です。